一、行政権と内閣
次のページ・・・二、内閣の組織と内閣の権能
1つ前のページ・・・第14章四、国会の権能と議院の権能
一、行政権と内閣

内閣について説明します。


内閣は行政権を行使します(65条)。
行政とは国会が決めた法律や予算に基づいて、実際に国の政治を行なうことです。
警察、社会福祉、教育、道路や橋の建設、などの仕事を行なっているのが行政です。
例として警察を挙げると、国会は犯罪者を取り締まり、国民の安全を確保する法律を制定しています。
その法律に基づいて行政が警察によって国民の安全を確保しているのです。
第65条 行政権は、内閣に属する。
| 内閣は行政権を行使: 例として警察を挙げると、国会は国民の安全を確保する法律を制定し、その法律に基づいて、行政が警察によって国民の安全を確保している。 |
 |
 |
 |
| 1 行政権の概念 |

警察、社会福祉、教育、道路や橋の建設などかー。行政の仕事ってすごくたくさんあるんだねー。

その通りです。
行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残り全ての作用である、とされています(控除説)。
つまり立法関係のものでもなく、司法関係のものでないものは、すべて行政関係のものになる、ということです。

ひゃー!でもそんなたくさんの仕事、内閣だけで出来るモンなの?
| 2 独立行政委員会 |

そうですね。行政の仕事はたくさんあります。
内閣だけではこなしきれません。
そこで憲法のもと、国家行政組織法などの法律によって、内閣を頂点として多くの行政機関が設けられたくさんの仕事をこなしています。
図で示すと内閣はこのような組織になっています(2022年現在)。


内閣官房HP行政機構図より抜粋

ここで問題となるのが、独立行政委員会の存在です。
独立行政委員会には人事院、中央労働委員会、公正取引委員会、国家公安委員会、などがあります。
独立行政委員会は職権行使にあたって独立で委員の身分が保障されています。
行政の組織のなかで独立性が認められているのです。
例えば中央労働委員会では労使間の争議の調整をします。
この調整は独立で中央労働委員会が行なうことができます。
こうした独立行政委員会の職権行使は憲法65条の「行政権は内閣に属する」という内容に反するのではないか、という問題が生じるのです。
| 中央労働委員会:内閣から独立して、独自の職権である労使間争議の調整ができる。 |
 |

独立行政委員会は憲法65条に反しない、とするのが今日の通説です。
しかしその解釈の仕方は2つに分かれています。
A説は、行政委員会も内閣のコントロール下にあり、合憲である、とする説。
B説は、憲法は内閣はすべての行政について指揮監督権を要求しているものではないから合憲である、とする説。
以上の2説が争われています。
A説が支持される理由は、内閣は委員の任命権・委員の予算編成権を持っているから独立行政委員会は内閣のコントロール下にある、とするものです。
しかし任命権・予算編成権があるというだけで内閣のコントロール下にあるとするなら裁判所についても同様になってしまう、という批判もあります。
B説が支持される理由は、
①65条が「すべて行政権は」とは述べていない、
②65条の行政権は政治的作用のことを述べており、非政治的作用は含まれない、
③行政権が内閣に属するのは立法権・司法権が内閣に属しないことに意味があるから内閣以外の機関が行政権を行使しても権力分立に反するといえない、
などが挙げられます。
A説とB説をまとめると、このようになります。
| A説:65条は一切の例外を認めていない、と考える説 | ||||
| 結論 | 行政委員会も内閣のコントロール下にあり、合憲である。 | |||
| 理由 | 内閣は、委員の任命権・委員の予算編成権を持っているから、独立行政委員会は、内閣のコントロール下にある。 | |||
| 批判 | 任命権・予算編成権があるというだけで、内閣のコントロール下にあるとするなら、裁判所についても同様になってしまう。 | |||
| B説:65条は一定の例外を認めている、と考える説 | ||||
| 結論 | 憲法は、内閣はすべての行政について指揮監督権を要求しているものではないから、合憲であるとする。 | |||
| 理由 | ①65条が「すべて行政権は」とは、述べていない。 ②65条の行政権は、政治的作用のことを述べており、非政治的作用は含まれない。 ③行政権が内閣に属するのは、立法権・司法権が内閣に属しないことに意味があるから、内閣以外の機関が行政権を行使しても、権力分立に反するといえない。 | |||
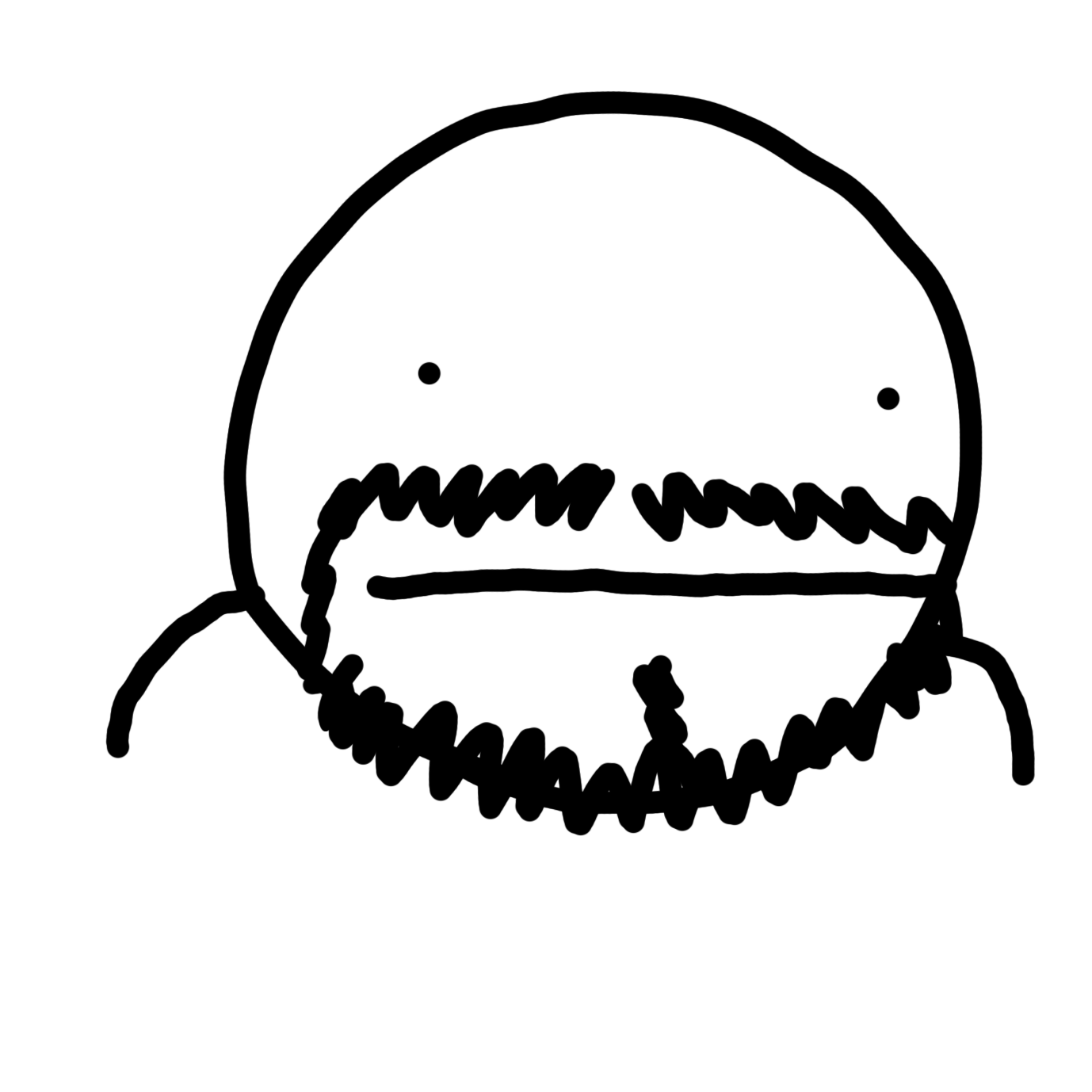
ちょっと難しいな、と思う方は結論の「独立行政委員会は合憲である」ということだけおさえてください。
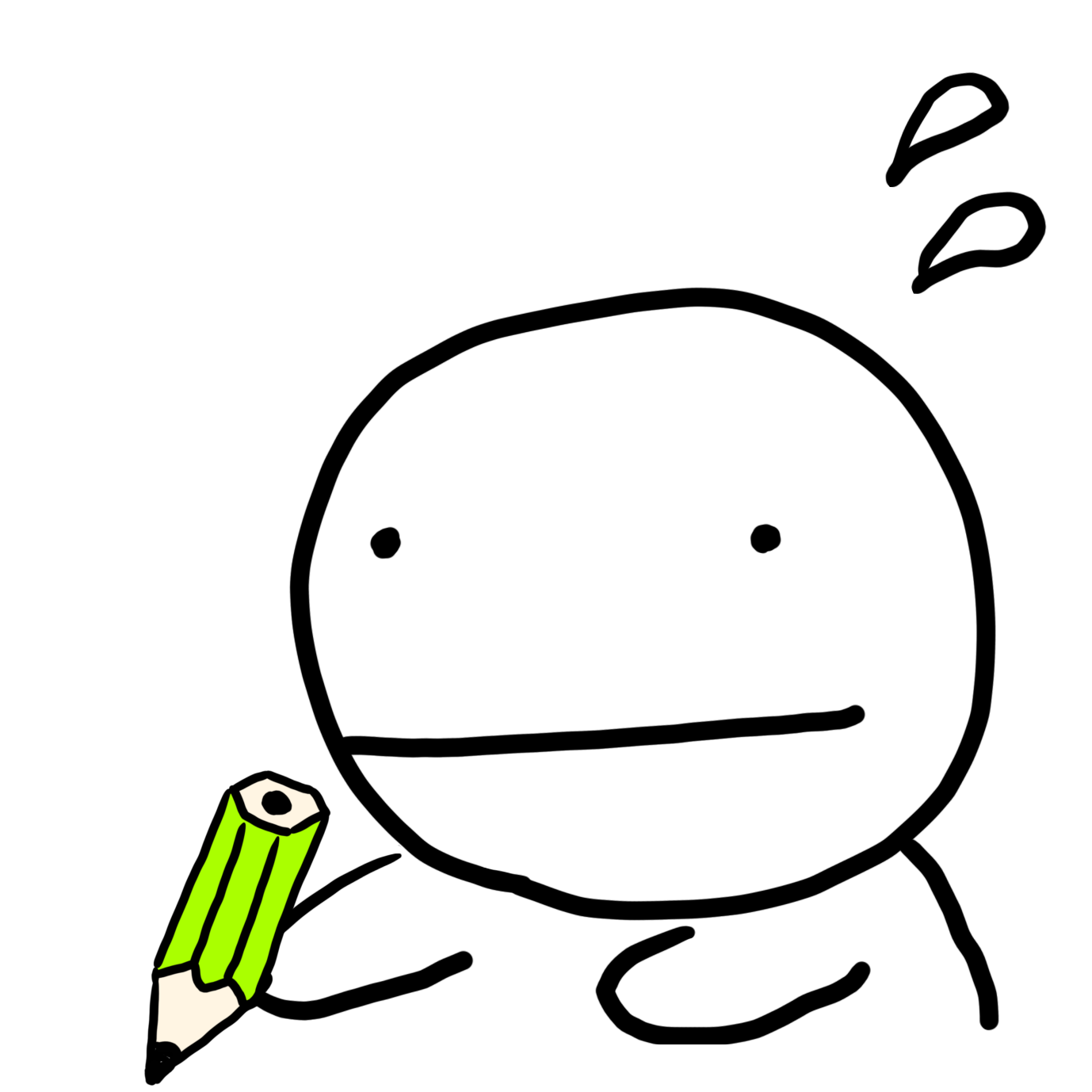
【まとめ】
第3部 統治機構
第15章 内閣
一、行政権と内閣
1、行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残り全ての
作用である、とされている(控除説)。
2、独立行政委員会は憲法65条の「行政権は内閣に属する」の趣旨に反しない、と
されている。
しかしその解釈の仕方はA説とB説の2つに分かれている。
A説:行政委員会も内閣のコントロール下にあり、合憲である、とする説。
B説:憲法は内閣はすべての行政について指揮監督権を要求しているものでは
ないから合憲である、とする説。
第3部 第15章 内閣 一、行政権と内閣 おしまい
次のページ・・・二、内閣の組織と内閣の権能
1つ前のページ・・・第14章四、国会の権能と議院の権能
