三、被告人の権利
次のページ・・・第12章一、生存権
1つ前のページ・・・二、被疑者の権利
三、被告人の権利

憲法37条~39条では刑事裁判手続に関する規定を設けています。
刑罰を科すことを科刑といいます。
その科刑の手続に関するものです。
先にも述べましたが刑罰は人にとってすごく重大なものです。
したがってその刑罰を科す手続は慎重で公正なものでなければなりません。
これから刑事裁判手続に関する規定を6つ説明します。
被告人とは何らかの犯罪を犯した疑いがあって、訴えられている側の人のことです。
| 刑事裁判手続の流れ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利 |

1つ目、37条では公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を保障しています。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
つまり裁判は公平・迅速・公開の要件を充たす必要がある、と規定しています。
| 公平・迅速・公開の要件を充たす裁判 |
| 公平の要件を充たす裁判:裁判官が公平な第三者として予断を排除して判断すること。 そのため裁判官の除斥、忌避、回避の制度がある。 |
| 除斥:所定の事由がある場合、その裁判官がその職務から排除されること |
 |
| 忌避:検察官等の申立てによりその裁判官がその職務から排除されること。 |
 |
| 回避:その裁判官自らその職務から退くこと。 |
 |
| 迅速の要件を充たす裁判:すばやく審理して不当な遅延のない裁判をすること |
 |
 |
 |
 |
| 公開の要件を充たす裁判:判決が公開の法廷で行われること。 |
 |

まとめて言うと、公平な裁判所の迅速な公開裁判の制度を保障している、ということになるのです。
| 2 証人審問権・喚問権 |

2つ目、憲法37条2項では証人審問権・喚問権を保障しています。
第37条
2項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

この条文は2つに分けられます。
①刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる
②公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する
①を前段、②を後段、といいます。
①前段は、被告人が証人に対して質問する権利を保障しています。
証人が証言したことに対して、被告人の言い分を聞いてあげる機会をきちんと与えなければ、証人の証言には証拠として認められません。
| 証人審問権:被告人が証言に対して質問する権利を保障する。 |
 |
 |

証人に対して質問する権利を規定することによって、被告人が検察官と対等な立場になることを保障しています。
②後段は、被告人が公費で自分にとって有利な証人を呼ぶ権利を保障しています。公費とは国家のお金のことです。
| 証人喚問権:被告人は、公費で自分に有利な証人を呼ぶ権利が保障されている。 |
 |
 |

えぇッ!?公費ってことは自分でお金を払わなくてもいいの?

確かに公費とは国家のお金のことであって、私費ではありません。
しかし、有罪判決が下された場合は、被告人に訴訟費用を負担するよう命じることは差し支えありません。
| 有罪判決が下された場合は、被告人に公費で費やした訴訟費用を、負担するよう命じてもよい。 |
 |

そりゃそうだよね。
| 3 弁護人依頼権 |

3つ目、憲法37条3項では被告人をサポートする制度である弁護人依頼権を保障しています。
第37条
3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
被告人は法的知識を持っていなかったり、身柄拘束を受けて精神的に辛い立場にあったりします。
弁護人は資格を持つ弁護士が行なうので、被告人の欠けている法的知識を補ったり、精神的に支えたりします。
被告人が弁護士に依頼できないときは国が弁護士をつけてあげます。
| 被告人をサポートする制度の、弁護人依頼権が保障されている。 |
 |
 |
| 4 黙秘権 |

4つ目、憲法38条1項では黙秘権を保障しています。
第38条
1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
簡単に言えば被告人は聞かれたことに対し黙っている権利がある、ということです。
| 黙秘権が保障されている。 |
 |
| 5 自白 |

5つ目、憲法38条2項、3項では自白強要からの自由を保障しています。
第38条
2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
38条2項は、強制的に吐かせた自白は証拠にならないことを規定しています(自白排除の法則)。
| 自白排除の法則:強制的に吐かせた自白は証拠にならない。 |
 |

38条3項は、強制的に吐かせた証拠でなくてもこれを補強する証拠が他にない限り有罪の証拠にならないことを規定しています(補強証拠の法則)。
| 補強証拠の法則:強制的に吐かせた証拠でなくても、これを補強する証拠が他にない限り、有罪の証拠にならない。 |
 |
| 6 事後法と「二重の危険」の禁止 |

6つ目、憲法39条では刑罰不遡及・二重処罰の禁止を規定しています。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
刑罰不遡及・二重処罰の禁止とは一定の行為の後に、当該行為を取り締まる法律を定めて罰することは許されない、ということです。
例えば2010年1月に改正著作権法が施行されました。
以前は私的利用目的なら音楽のダウンロードが自由にできました。
しかし、著作権法改正により音楽をダウンロードすることは違法行為となりました。社会的状況が変化したのです。
このとき、「オマエは2009年に音楽ダウンロードしてたから処罰する!」という風に、処罰されたらたまったものではありません。
こうしたことを禁じているのです。
| 刑罰不遡及・二重処罰の禁止:一定の行為の後に、当該行為を取り締まる法律を定めて罰することは許されない。 |
 |
 |
 |

うん、そんな風に処罰されたら困るよ。

以上、憲法37条~39条の刑事裁判手続に関する規定、6つの説明でした。
| 7 残虐刑の禁止 |

憲法36条では残虐刑の禁止を規定しています。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
刑事手続だけでなく全ての公務員の残虐な刑罰を禁止しています。
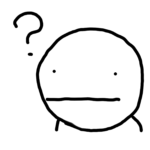
なるほどね。でも普通に「禁止する」でいいのに、なんで「絶対に禁止する」なんて規定してるの?

日本国憲法の条文で何かを禁止している条文は他にもいくつかあります。
しかし、36条だけ「絶対に禁止」と規定されています。
明治憲法下ではしばしば公務員による残虐刑が行なわれていました。
そうした歴史的背景の反省から2度と同じ過ちを犯さないよう「絶対に禁止」と規定しています。
判例は、残虐刑とは不必要な苦痛のある残酷な刑、と示しています。
具体的には火あぶり、はりつけ等がその例です。
| 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止されている。 |
 |
 |

うわー、明治憲法下の時代は怖いなぁー。
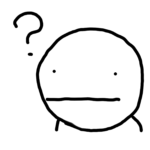
アレ!?でも死刑は?死刑は残虐な刑じゃないの?

死刑は日本では絞首刑を執行します。
絞首刑とは、受刑者の首に縄をかけて絞り首にして生命を奪う刑です。
これは残虐刑にあたるのではないか、死刑は廃止せよ、という論者と、死刑は残虐刑ではない、存続させよ、という論者が対立しています。
日本では現在も死刑制度は存続していて、対立は絶えることがありません。
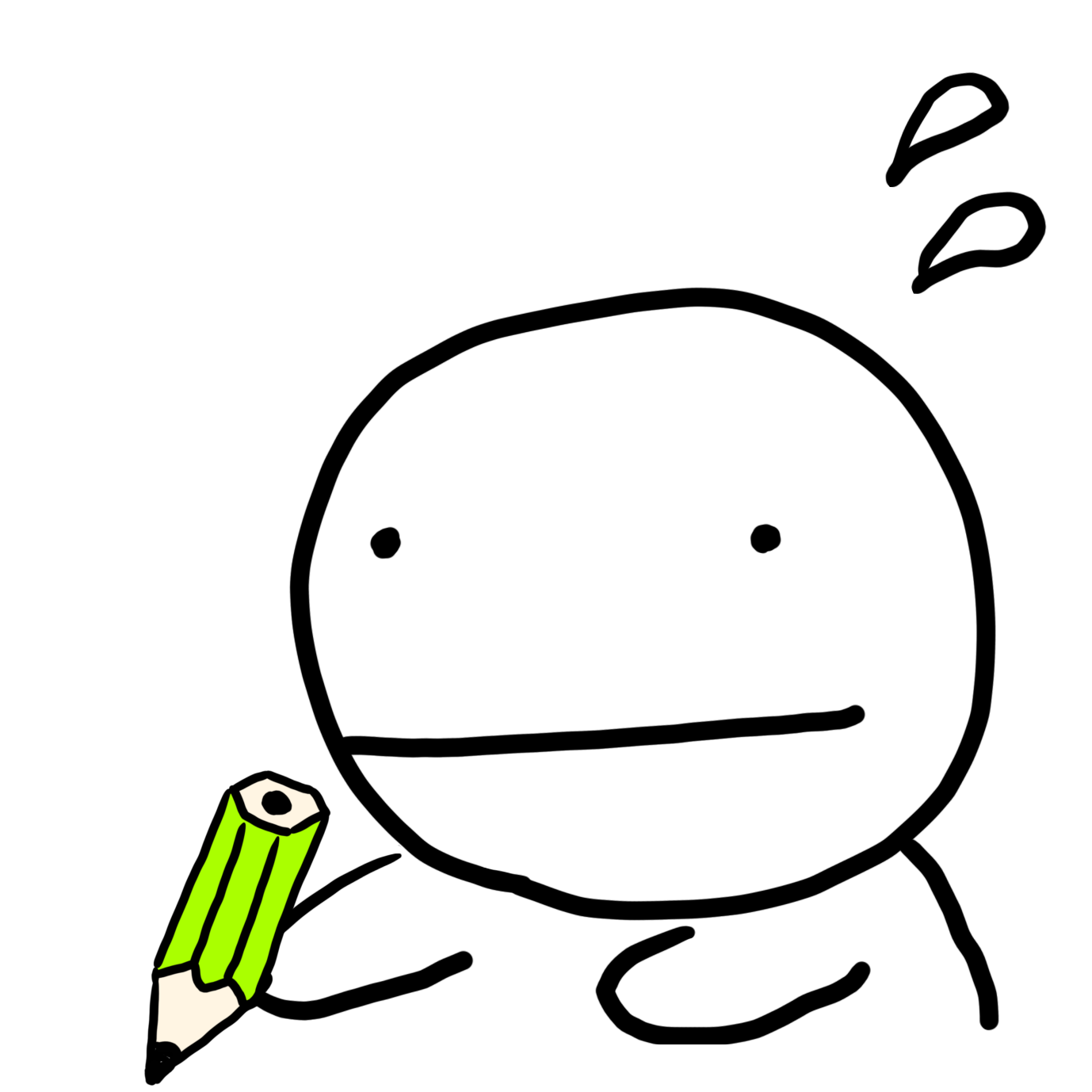
【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第11章 人身の自由
三、被告人の権利
1、37条1項では公平な裁判所の迅速な公開裁判の制度を保障している。
2、37条2項では証人審問権・喚問権を保障している。
3、37条3項では弁護人依頼権を保障している。
4、38条1項では黙秘権を保障している。
5、38条2項では自白排除の法則、38条3項では補強証拠の法則を定めている
(自白強要からの自由を保障)。
6、39条では刑罰不遡及・二重処罰の禁止を定めている。
↑憲法37条~39条で刑事裁判手続に関する規定を設けている。
7、36条では残虐刑の禁止を定めている。
第2部 第11章 人身の自由 三、被告人の権利 おしまい
次のページ・・・第12章一、生存権
1つ前のページ・・・二、被疑者の権利
